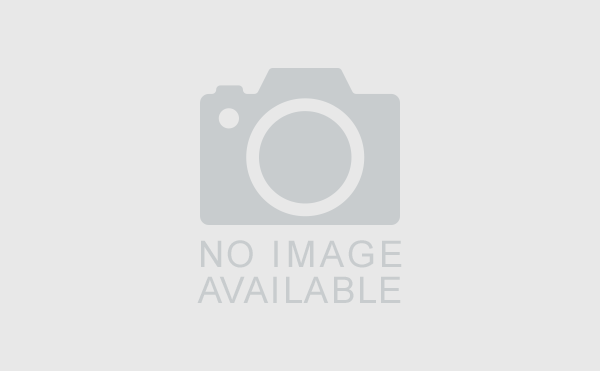小学生の不登校、最初に親がすべきこと3選
不登校という言葉に、戸惑いや不安を抱えていませんか?
この記事では、小学生の不登校に悩む親御さんが、今できること・心がけたいこと3選をやさしく具体的にお伝えします。
小学生の不登校を実際に経験したことも盛り込んでいますので、少しでも心が軽くなればと思います。

- 子どもに必要な環境を整える
- 不登校の理由を“理解”するための時間をとる
- スクールカウンセラー・児童生徒支援センターなどの支援機関に相談する
1.子供に必要な環境を整える
小学生の不登校に直面した際、保護者が最初に取るべき行動は、子どもの心に寄り添い、安心できる環境を整えることです。
文部科学省の調査によれば、不登校の背景には「無気力」「不安」「人間関係の悩み」など、子ども自身も言葉にしづらい心理的要因が多く含まれています。
まず大切なのは、「学校に行かせなければ」と焦るのではなく、子どもの気持ちを受け止める姿勢です。
今、子供に必要なのは絶対的に安心できる環境なのです。
「どうして行けないの?」と問い詰めるのではなく、「つらかったね」「話してくれてありがとう」と共感の言葉をかけることで、子どもは安心感を得られます。
「親(家)は自分を守ってくれている」という感覚を持たせると良いでしょう。
このような親との信頼関係の構築が、再び前向きな気持ちを育む土台となります。
2.不登校の原因についての理解を深めよう
不登校の背景には、いじめや学業の不振、家庭内の問題、発達障害など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。mext.go.jp+2osakachild.com+2k-luck.com+2
家庭内の問題も少なからずあり、親としては耳の痛い話です。
子どもは自分と別人格であり、予想もしないところでつまずいたり傷ついたりしていることがあります。
「こういう風に感じるのかな」「こういうタイプもいるんだ」という他者を受け入れる準備が親には絶対に必要と感じます。
そして、それには時間が必要なこともお伝えしておきますね。
小学生のうちは特に気持ちを言語化することは難しいので、そのまま受け取らず、日常の様子や変化に注意を払いながら、子どもの気持ちに寄り添う姿勢が求められます。
案外、授業の進行スピードについていけてなかったり、先生と合わなかったりするかもしれません。
子供の特性と環境がマッチしない場合だってあります。子供の特性を知ることも非常に大切です。
我が子は、かなりこだわりが強く、ペースを乱される集団生活が苦痛だったことが、おそらくきっかけでした。
おそらく、としか言えないのは本人もちゃんと言語化できなかったからですが、私自身がいろいろ知識を得て体験とすり合わせたりした結果、何年も経ってから思いつく原因のひとつです。
不登校は子どもが発するSOSのサインでもあり、親が他者を理解するきっかけになります。時間をかけながら、ともに成長できるので、焦らずじっくり取り組んでみてください。
3. 専門家の助けを借りてみよう
地域の教育支援センターやスクールカウンセラーなど、専門機関への相談も検討しましょう。
これらの機関では、子ども一人ひとりの状況に応じたサポートを提供しており、保護者自身の不安や悩みを共有する場としても活用できます。
私自身、こういった機関に相談するのには抵抗がありました。
自分でどうにか情報を集めて、知りたい情報だけかき集めてなんとかごまかしてやっていました。
でも、親が一人でできることは限られています。時間もないし、専門用語もわからない。
そんなとき、勧められたのがスクールカウンセラーや地域の教育委員会が提供している親子カウンセリングです。
私の場合は、これらの活用で何かが改善した!ということはなかったのですが、相談できるところがある、というのは大きかったですし、何よりも同じような不登校になった子たちが、どのようになっていくのかなどの生の知識を頂けたことが、良かったことでした。
「事実を知る」ということは、先の未来を考えるうえで非常に重要なポイントでした。
まとめ
不登校は、子どもが自分自身と向き合い、成長するための一つのプロセスです。
そして、子どもの不登校は、親にとっても心が揺れる経験です。
でも大切なのは、「学校に行くかどうか」よりも、子どもの心が少しずつ元気を取り戻すこと。
まずは安心できる居場所を家庭に作り、焦らず、信じて見守ることから始めましょう。
親自身がゆるむことも、子どもに安心感を届ける大切な要素です。
ひとつひとつ、小さな一歩でかまいません。
親子にとっての「これから」を共に育んでいけるよう、必要なときは周囲の支援にも頼ってくださいね。